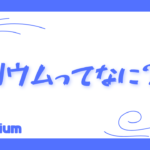トイレリウム(Toiletrium)は、この言葉は「トイレ」と「テラリウム」を組み合わせた造語であり、トイレ空間に植物やアクアリウム、テラリウムなどの自然的要素を取り入れることで、機能的な空間を癒しと安らぎの場所へと転換する現代的な自然回帰の傾向の概念である。
近代のトイレ空間の歴史
近代のトイレ空間の歴史は、単なる生理現象を解消する場から、快適性や居心地を重視した空間へと進化してきた。
明治時代に洋式トイレが日本に入ってきた。1887年には横浜の外国人居留地に英国製の洋式水洗トイレが設置され、これは日本における水洗トイレの初期の例として知られている。
1914年(大正3年)には、東洋陶器(現・TOTO)が日本で初めて陶器製の水洗トイレの国産化に成功した。大正時代には都市部を中心にトイレの洋式化が徐々に進んだが、水洗トイレの設置には下水道整備が不可欠なため、その普及は限定的であった。
関東大震災(1923年)後の復興過程で下水道の整備は進められたが、一般家庭への水洗トイレの本格的な普及は、第二次世界大戦後の高度経済成長期を待つことになる。
昭和30年代(1950年代後半)には住宅公団による集合団地への水洗トイレ導入が進み、主に都市部での普及が始まった。この時期、トイレは効率性や実用性を重視したシンプルなデザインが主流であった。1960年代後半から1970年代にかけて下水道網の拡大とともに水洗トイレの普及率が段階的に上昇し、人々の生活環境における衛生面での向上が進んだ。
20世紀後半からは、人々の価値観や生活様式の変化に伴い、トイレ空間も新たな段階へと進化した。1980年に温水洗浄便座「ウォシュレット」が商品化され、1980年代以降その普及とともにトイレの快適性は飛躍的に向上した。1985年頃からトイレは単なる排泄の場ではなく、リラックスや癒しを提供する空間として認識されるようになった。1990年代に入ると、観葉植物や花など自然要素を取り入れる試みが広まり、視覚的な心地よさやリラクゼーション効果が重視されるようになった。また、音姫などの水音装置や自然光、間接照明を活用した照明デザインなども採用されるようになり、トイレ空間はより居心地の良い場所へと変貌した。
この歴史を通じて、日本のトイレ文化は機能性と快適性を両立させながら発展してきたことが分かる。単なる排泄の場から居心地の良い空間への変貌は、人々の日常生活や価値観の変化と密接に結びついており、このような快適性と癒しを重視した現代のトイレ空間は”トイレリウム”と呼ばれるようになった。
トイレリウムの分類と特徴
主に居心地の良い空間を生み出すトイレリウムには下記の手法が取り入れられる。
アクアテラリウム型
一つ目はアクアテラリウム型である。これはさらに二つのタイプに分かる
アクアリウムタイプ
アクアリウムタイプは、小型水槽による水中景観。水場であるトイレとアクアリウムは相性が良い。
熱帯魚やメダカ、金魚の魚と水草を用いて水中を表現する。熱帯魚のネオンテトラやグッピー、改良メダカなど小型魚を群で泳がせることで、動きのある癒しの空間が創出される。
- 小型水槽による水景観演出
- 熱帯魚(ネオンテトラ、グッピー)や金魚による動きのある演出
- 水草を配置し水中を表現
- 和風水槽は日本庭園的な景観表現も可能
テラリウムタイプ
テラリウムタイプで、ガラス容器内での小型植物による陸上景観。閉鎖的なガラス空間で創作された独特の世界観を、ミニチュアの庭園のような空間で植物育成ができる。
- ガラス容器内での陸上景観演出
- 苔や小型観葉植物によるミニチュア庭園的空間
- 閉鎖的なガラス空間での安定した湿度管理が特徴
植物開放型
植物開放型は季節の花を活けた小型の花瓶による装飾を行う生花と、テーブルサイズの小型観葉植物による緑の演出を行う観葉植物の二種類がある。
テラリウムタイプとの違いはガラス容器などの閉鎖的空間ではなく、植木鉢などをそのまま設置する点である。エアプランツなども活用される。
- 生花・造花
- 季節の花を活けた小型花瓶による装飾
- ドライフラワーアレンジメントによる演出
- 観葉植物
- ミニサボテンなどのテーブルサイズの小型観葉植物
- エアプランツなど管理の容易な種類も活用
これらの設置に際しては、トイレ空間に合わせたコンパクトなサイズ設計、清掃や維持管理の容易さ、空間の雰囲気との調和、限られた空間での効果的な配置、衛生面への配慮などが重要な考慮点となる。各タイプに応じた設備の整備も不可欠だ。
まず、トイレ照明とは別に、植物育成用の専用照明が必要となる。アクアリウムタイプの場合は、さらに環境維持機器として水質フィルターや水温管理システムの設置が求められる。
維持管理の面では、結露やカビ対策、植物の生育状態確認、病害虫対策などへの対応が必要であり、同時にトイレ清掃のしやすさへの配慮も欠かせない。植物型の場合は、灌水や給水の必要があるが、これはトイレ使用時に行うことで効率的な管理が可能である。
これらすべてのタイプに共通して、照明のタイマー制御システムや温湿度計などの基本的な環境管理設備の設置が必要となる。
トイレリウム
現代の機能性を備えたトイレ空間に、アクアリウムやテラリウム、植物などの自然的要素を効果的に取り入れ、維持管理に配慮しながら癒しの空間を創出する、新しいインテリアデザインの手法と呼べるかもしれない。
- 水槽のグリーンウォーター対処法 水質改善メダカの水槽がグリーンウォーターで濁ってしまい、愛するメダカたちの姿がよく見えない!そんな状況で悩んでいません…
- トイレに水槽は置けない?12の問題点を徹底検証してみたトイレリウムを始めようと思ったけれど、「トイレに水槽を置くなんて、衛生面が心配」「スペースがない」「メンテナン…
- 金魚の尾びれ異変!白いモヤはなに?水カビ病と尾腐れ病の対処法寒さが日に日に厳しくなり、水道水が冷たく感じる季節になってきました。ダーティーシゲオです。実は先日、夏祭りの思…
- ◯◯リウムってなに?テラリウム、アクアリウム、メダカリウム「様々な生態環境の再現術!~リウムの世界へようこそ」 リウムって聞いたことありますか?水槽や容器の中に、小さな…